

宅建 合格発表 2024の日程と時間
2024年度の宅建試験合格発表は、2024年11月26日(火)。
例年、試験日から26日後(土日祝日を除く)に発表されることが通例となっています。
合格発表の時間は、午前9時30分からとなっています。この時間から、一般財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイトで合格者の受験番号が公開されます。
注目すべき点として、合格発表日は平日に設定されていることが多いため、仕事や学校がある方は事前に確認方法を把握しておくことが重要です。
宅建の合格点と合格率
宅建試験の合格点(合格ライン)は、50点満点中35点前後に設定されることが多いです。ただし、試験の難易度によって若干の変動があります。
宅建試験の合格率は、例年15%から17%程度で推移しています。令和5年度(2023年度)の合格率は17.2%でした。この数字は、約6人に1人が合格するという難易度を示しています。
合格ラインについては、50問中35問から38問程度の正解が必要とされています。令和5年度の場合、合格ラインは50問中36問以上(登録講習修了者は45問中31問以上)でした。
ここで注目すべき点は、合格ラインが年によって変動するということです。これは、試験の難易度や受験者の平均点によって調整されるためです。
過去10年間の合格ラインの推移を見てみましょう:
| 年度 | 合格ライン | 合格率 |
|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 36点 | 17.2% |
| 令和4年(2022年) | 36点 | 17.0% |
| 令和3年(2021年) | 34点 | 17.9% |
| 令和2年(2020年) | 38点 | 17.6% |
| 令和元年(2019年) | 35点 | 17.0% |
この表から、合格ラインが34点から38点の間で変動していることがわかります。つまり、確実に合格を狙うなら40点以上を目指すのが賢明です。
興味深い点として、合格点と合格率には相関関係があり、試験が難しかった年は合格点が下がる傾向にあります。これは、受験者全体の得点分布を考慮して合格ラインが決定されるためです。
宅建試験の難易度 偏差値の具体的な数値
宅建試験の偏差値は、一般的に55〜57程度とされています。この数値は、他の国家資格と比較してもそれほど高くはありませんが、決して低いわけでもありません。宅建試験の特徴として、法律や不動産取引に関する専門的な知識が必要とされるため、一定の難易度があると言えるでしょう。
宅建試験の偏差値を他の資格試験と比較してみましょう。
| 資格名 | 偏差値 |
|---|---|
| 宅建士 | 55〜57 |
| 行政書士 | 60〜62 |
| 司法書士 | 65〜67 |
| 公認会計士 | 70〜72 |
宅建試験は他の法律系資格と比べると比較的取得しやすい資格であることがわかります。しかし、決して簡単ではなく、適切な学習計画と努力が必要です。
宅建試験の難易度 偏差値の具体的な数値
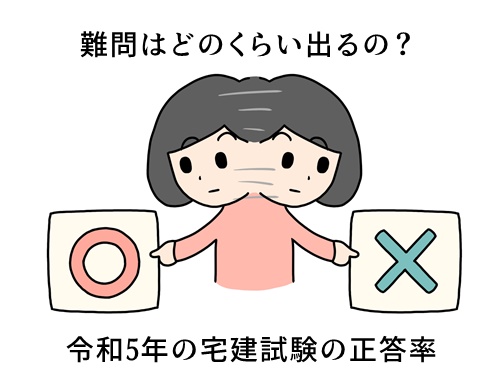
宅建試験の難易度を知るために、過去の試験の正答率を見ていきましょう。
以下は、宅建受験者のアンケートから個別問題の難易度を割り出したデータです。(令和5年度版)
正答率ごとに、易、標準、やや難、難と評価しています。
| 設問 | 正答率 | 難易度 |
|---|---|---|
| 問1 | 80.3% | 易 |
| 問2 | 56.1% | やや難 |
| 問3 | 76.5% | 標準 |
| 問4 | 59.8% | やや難 |
| 問5 | 56.8% | やや難 |
| 問6 | 26.5% | 難 |
| 問7 | 28.8% | 難 |
| 問8 | 68.9% | 標準 |
| 問9 | 52.3% | やや難 |
| 問10 | 45.5% | やや難 |
| 問11 | 63.6% | 標準 |
| 問12 | 70.5% | 標準 |
| 問13 | 84.1% | 易 |
| 問14 | 81.8% | 易 |
| 問15 | 86.4% | 易 |
| 問16 | 79.5% | 標準 |
| 問17 | 96.2% | 易 |
| 問18 | 58.3% | やや難 |
| 問19 | 84.1% | 易 |
| 問20 | 72.0% | 標準 |
| 問21 | 76.5% | 標準 |
| 問22 | 87.1% | 易 |
| 問23 | 88.6% | 易 |
| 問24 | 62.1% | 標準 |
| 問25 | 86.4% | 易 |
| 問26 | 76.5% | 標準 |
| 問27 | 78.0% | 標準 |
| 問28 | 93.2% | 易 |
| 問29 | 87.1% | 易 |
| 問30 | 77.3% | 標準 |
| 問31 | 87.1% | 易 |
| 問32 | 84.8% | 易 |
| 問33 | 71.2% | 標準 |
| 問34 | 78.0% | 標準 |
| 問35 | 90.2% | 易 |
| 問36 | 85.6% | 易 |
| 問37 | 92.4% | 易 |
| 問38 | 45.5% | やや難 |
| 問39 | 75.8% | 標準 |
| 問40 | 95.5% | 易 |
| 問41 | 62.9% | 標準 |
| 問42 | 82.6% | 易 |
| 問43 | 95.5% | 易 |
| 問44 | 96.2% | 易 |
| 問45 | 91.7% | 易 |
| 問46 | 95.7% | 易 |
| 問47 | 85.1% | 易 |
| 問48 | 33.9% | 難 |
| 問49 | 93.9% | 易 |
| 問50 | 80.9% | 易 |

基礎をガチガチに固めて挑めば、合格圏に充分入れる難易度と言えるでしょう。
宅建 合格発表 2024の確認方法と注意点
合格発表の確認方法は主に3つあります:
- ウェブサイトでの確認
一般財団法人不動産適正取引推進機構の公式サイトで、受験番号を入力することで合否を確認できます。最も早く結果を知ることができる方法です。 - 郵送による通知
合格者には合格証書が簡易書留で郵送されます。通常、合格発表日当日に発送されるため、数日後に受け取ることができます。 - 掲示による確認
各都道府県の指定場所に合格者の受験番号が掲示されます。掲示場所や期間は地域によって異なるため、事前に確認が必要です。
注意点として、電話やメールでの合否照会は受け付けていません。また、不合格者への個別通知はありません。
宅建 合格発表 2024後の手続きと登録方法
合格後、宅地建物取引士として活動するためには、以下の手続きが必要です:
- 登録の申請
合格から3年以内に、都道府県知事に登録申請を行う必要があります。 - 実務経験の証明
宅建業に関する2年以上の実務経験が必要です。実務経験がない場合は、登録実務講習を受講することで代替できます。 - 宅地建物取引士証の交付申請
登録後、宅地建物取引士証の交付を申請します。この証書が実際の業務で必要となります。
意外な情報として、登録実務講習は合格前でも受講可能です。事前に受講しておくことで、合格後すぐに登録申請ができるというメリットがあります。
宅建合格ライン予想の仕組みと変動要因
宅建試験の合格ライン予想は、試験の難易度や受験者の実力を考慮して行われます。主な変動要因には以下のようなものがあります:
・試験問題の難易度
・受験者数の増減
・法改正の有無
・社会経済情勢の変化
宅建合格ライン予想の公表時期と予備校別の特徴
宅建試験の合格ライン予想は、通常、試験当日の夕方から翌日にかけて各予備校から公表されます。主要な予備校の特徴は以下の通りです:
- ユーキャン
- 特徴:比較的早い段階で予想を発表
- 予想の傾向:やや控えめな予想を出す傾向
- TAC
- 特徴:詳細な分析レポートを提供
- 予想の傾向:中庸な予想を出すことが多い
- LEC
- 特徴:複数の予想を段階的に発表
- 予想の傾向:やや高めの予想を出す傾向
- 日建学院
- 特徴:地域別の予想も提供
- 予想の傾向:比較的正確な予想で知られる
- 大原
- 特徴:過去の傾向を重視した予想
- 予想の傾向:保守的な予想を出すことが多い
各予備校の予想には特徴があるため、複数の予備校の予想を比較検討することが重要です。また、予想は試験終了直後から翌日にかけて段階的に更新されることがあるため、最新の情報をチェックすることをおすすめします。
宅建合格ライン予想と実際の合格点の比較分析
宅建試験の合格ライン予想と実際の合格点を比較分析することで、予想の精度や傾向を把握することができます。過去5年間の予想と実際の合格点を比較してみましょう。
| 年度 | 主要予備校の予想平均 | 実際の合格点 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36点 | 37点 | +1点 |
| 2022 | 35点 | 34点 | 1点 |
| 2021 | 33点 | 35点 | +2点 |
| 2020 | 36点 | 35点 | 1点 |
| 2019 | 34点 | 33点 | 1点 |
この表から、以下のような傾向が見られます:
- 予想の精度
- 概ね1〜2点の範囲内で予想が的中していることがわかります。
- 予想のばらつき
- 年によって予想が高めになったり低めになったりすることがあります。
- 合格点の変動
- 実際の合格点も年度によって変動しており、33点から37点の範囲で推移しています。
- 予想の保守性
- 予備校は若干低めの予想を出す傾向があります。これは受験者の不安を和らげる効果があります。
- 難易度との相関
- 試験の難易度が高いと感じられた年は、実際の合格点が予想より低くなる傾向があります。
この分析から、合格ライン予想は概ね信頼できるものの、完全に正確ではないことがわかります。したがって、予想を参考にしつつも、余裕を持った得点を目指すことが重要です。
宅建合格発表の日程と時間
宅建試験の合格発表は、例年11月中旬から下旬にかけて行われます。令和5年度(2023年度)の場合、試験実施日から約1ヶ月後の11月21日(火)に発表されました。発表時間は通常午前10時頃となっています。
合格発表日は、試験実施機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構(以下、不動産適取)のウェブサイトで事前に告知されます。受験者は、この日程をチェックしておくことが重要です。
合格発表日当日は、不動産適取のウェブサイトにアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性があります。そのため、発表直後はアクセスを控え、少し時間をおいてから確認するのも一つの方法です。
宅建合格発表で確認できる情報
合格発表日に確認できる情報は主に以下の3点です:
- 合格者の受験番号
- 合格基準点(合格ライン)
- 合格率
合格者の受験番号は、不動産適取のウェブサイトで公開されます。自分の受験番号が掲載されているかどうかで合否を確認できます。
個人の得点は発表されません。
しかし、点数を知る方法はあります。
試験の運用団体である、不動産適正取引推進機構に問い合わせることで請求できるんですね。
「絶対合格しているはずなのに!不合格なんて絶対おかしい!」と思ったあなたは有料ですが、請求してみるといいでしょう。
1)解答用紙(マークシート)の写し
2)マークした(と判定された)番号と実際の点数
1点あたり1,000円かかります。両方請求すると2,000円。
なお、どこかに問い合わせフォームがあるということはなく、「電話で問い合わせて開示請求手続きをする」という手順になります。
けっこうハードル高い…
関連)宅建「個人情報開示請求 手順と結果」 | 司法試験合格への道
宅建試験合格後の手続きと注意点
宅建試験に合格した後、宅地建物取引士として活動するためにはいくつかの手続きが必要です。
- 登録実務講習の受講
合格後2年以内に、登録実務講習を受講する必要があります。この講習は、実務に必要な知識やスキルを学ぶための重要なステップです。 - 宅地建物取引士証の交付申請
登録実務講習を修了後、都道府県知事に宅地建物取引士証の交付を申請します。この際、実務経験の証明が必要となります。 - 実務経験の確保
宅地建物取引士証の交付を受けるには、不動産取引の実務経験が必要です。具体的には、宅建業者のもとで2年以上の実務経験が求められます。 - 更新講習の受講
宅地建物取引士証の有効期限は5年間です。更新時には、更新講習の受講が必要となります。 - 倫理規定の遵守
宅地建物取引士には、高い倫理観が求められます。取引の公正を確保し、依頼者の利益を保護する責任があります。
注意点として、合格後5年以内に宅地建物取引士証の交付を受けない場合、合格が無効となる点が挙げられます。これは意外と見落とされがちな重要なポイントです。
以上、宅建合格発表に関する重要なポイントをまとめました。合格を目指す方々にとって、この情報が有益なものとなれば幸いです。宅建試験は難関ですが、適切な準備と正しい情報があれば、必ず突破できるはずです。頑張ってください。

