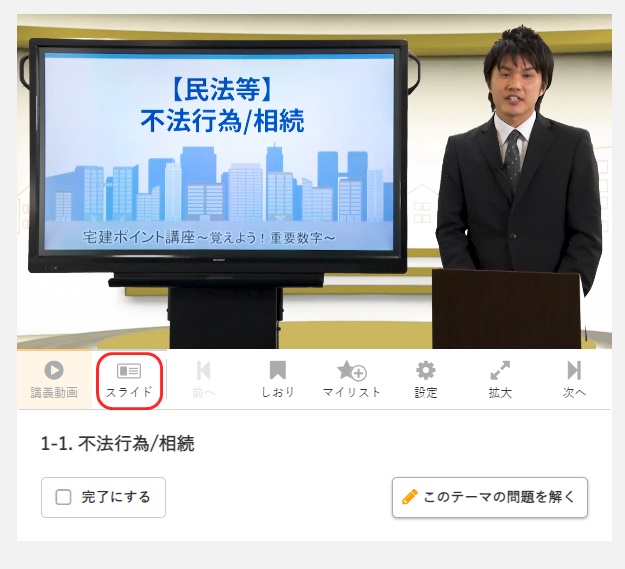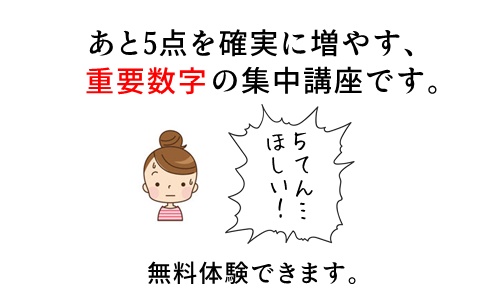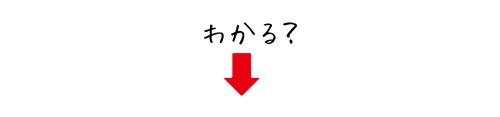全力で宅建合格

宅建試験で重要な留置権について、わかりやすく解説します。留置権の基本概念から具体例、試験対策のポイントまで網羅的に紹介しますが、留置権の意外な側面とは?
留置権をわかりやすく宅建試験対策で解説
留置権の基礎知識の一問一答
もう一度やるアプリでやる
留置権の成立要件と具体例
留置権の成立には、以下の4つの要件を満たす必要があります:
これらの要件を満たす具体例として、よく挙げられるのが自動車整備の事例です。お客さんが車検のために自動車をお店に預け、整備が完了したにもかかわらず代金を支払わない場合、お店は留置権を行使して車を引き渡さないことができます。
この事例では:
- お店がお客さんの車を占有している
- 整備代金請求権という債権が車に関して発生している
- 整備完了時点で代金支払いの期限が来ている
- 車の占有は合法的な契約に基づいている
したがって、留置権の成立要件を全て満たしています。
留置権の性質と効力
留置権には以下のような性質があります:
しかし、留置権には他の担保物権(質権、抵当権など)と異なり、優先弁済効力がありません。つまり、留置権者は目的物を競売にかけて債権を回収することはできません。
留置権の主な効力は:
最高裁判所の判例で、留置権の効力について詳しく解説されています。
宅建試験における留置権の出題傾向
宅建試験では、留置権に関する問題が頻出します。特に以下の点に注意が必要です:
- 留置権の成立要件
- 留置権と他の担保物権との違い
- 不動産に関する留置権の具体例
- 留置権の消滅事由
出題形式としては、正誤問題や選択問題が多く、具体的な事例を示して留置権が成立するかどうかを問う問題もよく見られます。
留置権と建物賃貸借の関係
建物賃貸借に関連して、留置権が問題となるケースがあります:
- 必要費償還請求権に基づく留置権
- 賃借人が建物の修繕などの必要費を支出した場合、その償還を受けるまで建物を留置できる
- 造作買取請求権と留置権
- 賃借人が付加した造作の買取請求をしても、その代金の支払いを受けるまで建物を留置することはできない
- 敷金返還請求権と留置権
- 賃貸借終了時、敷金返還請求権を理由に建物を留置することはできない
YouTubeで留置権と建物賃貸借の関係について詳しく解説されています。
留置権の意外な側面:商事留置権との比較
民法上の留置権(民事留置権)に対して、商法上の留置権(商事留置権)があることはあまり知られていません。両者の主な違いは:
- 牽連性の要件
- 民事留置権:必要
- 商事留置権:不要(債権と物との間に牽連性がなくても成立)
- 適用範囲
- 民事留置権:一般的な取引
- 商事留置権:商人間の取引に限定
- 優先弁済権
- 民事留置権:なし
- 商事留置権:あり(商法521条)
宅建試験では主に民事留置権が出題されますが、商事留置権との違いを理解しておくことで、留置権の本質をより深く理解できます。
以上、留置権について宅建試験対策の観点から解説しました。留置権は一見複雑に見えますが、基本的な概念を押さえれば十分に理解できる分野です。具体例を交えながら学習を進めることで、確実に得点源とすることができるでしょう。